「作りたい女と食べたい女」と検索すると、関連ワードに「炎上」「気持ち悪い」という言葉が並ぶのはなぜなのでしょうか。心温まる百合グルメ漫画として始まった本作が、今や議論と批判の的となっている背景には、ストーリーや表現の変化、そして読者とのズレが大きく影響しています。本記事では、28話の“山賊事件”をきっかけに加速した炎上の理由から、絵柄やテーマの変化、さらにはSNS上での作者の対応に至るまで、読者が抱える違和感の核心を掘り下げます。作品の魅力と課題を両面から見つめ直すことで、いま何が問われているのかを明らかにします。
1. 序章:「気持ち悪い」と検索する人が本当に知りたいこと
1-1. なぜ今、この作品が検索され続けているのか?
『作りたい女と食べたい女』(通称「つくたべ」)が、2024年後半から急激に検索されるようになった背景には、作品を取り巻く“異常な注目度”と“炎上の連鎖”があります。特に注目が集まったのは、Web連載第28話で起きた、いわゆる「山賊騒動」。物語の中で登場人物たちが、他人の家の食材を無断で使用するというシーンが描かれ、それがSNS上で「モラルがない」「山賊行為では?」と一斉に叩かれました。この一件をきっかけに、作品に対する批判が一気に噴き出し、それまで感じられていた小さな違和感も掘り起こされていったのです。
その後、検索される理由は単なる好奇心ではなく、「なぜこんなに荒れているのか?」という真相を探る動機へと変わっていきます。特に「気持ち悪い」「炎上」といった検索ワードが並ぶのは、ただの炎上騒動ではなく、作品に対して根本的な拒否感を抱いている人が多いことの表れです。
また、2024年にはNHKでのドラマ化も進み、実写版でもローストビーフの調理法をめぐる安全性の問題がニュースに。これによって、作品そのものだけでなく、原作を取り巻く制作体制や作家の姿勢までもが注目されるようになり、検索ボリュームがさらに拡大することになります。「つくたべ」がもともと穏やかな日常を描く百合作品として支持を集めていた分、その反動として炎上が大きくなる構造があるとも言えるでしょう。
1-2. “炎上”と“違和感”が交差する作品特性とは
この作品に対する反応が、単なる「批判」にとどまらず「気持ち悪い」という感情表現にまで及んでいるのは、単純な作画やストーリー展開の問題だけでは語れません。多くの読者が違和感を覚えたのは、表現の裏にある「価値観の押しつけ」や「説得力の欠如」といった、より根本的なレベルでのズレです。
例えば、作品内ではLGBTQ+のテーマが大きく扱われており、登場人物たちはセクシャリティに悩みながらも前向きに生きようとしています。しかし、その過程で描かれる困難の多くが、現実の当事者から見るとあまりに悲観的で一面的すぎるという指摘があります。特に、新居を探すエピソードでは、「同性カップルが安心して暮らせる物件を紹介してもらうには、当事者が運営する不動産屋に行くしかない」という展開が描かれ、実際に同様の経験をしている人々からは「現実を過度にネガティブに描きすぎている」との声が多数あがりました。
また、会食恐怖症や摂食障害のようなデリケートな症状についても、正確な知識や医療的配慮に欠けた描写が多く、専門家からの批判も相次ぎました。読者の中には、「理解してほしいというテーマで描いているのに、その理解が浅いことが透けて見えてしまう」と感じる人も少なくありません。
このように、作品の意図としては「多様性」や「共感」が掲げられていても、描写そのものがリアリティや配慮を欠いていたため、むしろ反感を買ってしまうという構造になっていたのです。そのギャップが、「炎上」と「気持ち悪い」という感情の両方を引き起こしている大きな要因と言えるでしょう。
2. 初期評価とのギャップがもたらした落差
2-1. 「心温まる百合×料理漫画」から始まったはずが…
もともと『作りたい女と食べたい女』は、「料理」と「百合」を組み合わせた癒し系日常漫画としてスタートし、SNSを中心に幅広い支持を集めていました。登場するのは、料理が大好きな女性・野本さんと、それを食べるのが何よりの楽しみである女性・春日さん。二人のやり取りには恋愛の気配はありつつも、恋愛そのものをゴリ押しせず、料理を通して静かに心の距離が縮まっていく様子が、多くの読者の共感を得ていました。
初期の頃は、キャラの繊細な表情や料理シーンの丁寧な描写などが特に好評でした。実際、料理の手順や食材の描き方にはリアリティがあり、レシピとしても参考にできるレベルのクオリティだったのです。登場人物が少なく、物語の密度が高いことも、読者にとって集中しやすく感情移入しやすいポイントとなっていました。
しかし、シリーズが進むにつれて、物語は次第に「料理×百合」の枠を超え、より社会的なテーマや登場人物の心の闇、セクシャリティの葛藤などを深く掘り下げる方向に移行していきます。この変化が一部の読者には“作品の成長”として歓迎された一方で、「こういうのが見たかったわけじゃない」という失望の声も増えていきました。
つまり、本来は「日常の癒し」を求めていた読者にとって、途中からの“社会派方向”への転換は、ある種の裏切りに感じられたのです。その違和感が、後に大きな批判へとつながっていく流れができていきます。
2-2. 読者の期待とのズレが炎上の土壌に
『つくたべ』が炎上した根本的な要因のひとつに、「作品の方向性と読者の期待のズレ」があります。これはジャンル自体の変化に限らず、物語の中で描かれる倫理観やキャラクターの行動、セリフの一つひとつが、読者の感覚と乖離していった結果です。
28話の「山賊騒動」はまさにその象徴的な出来事でした。登場人物が他人の家の備蓄食材を無断で使い、しかもそれを好意的に描いていたことが、読者の常識と真っ向から衝突したのです。さらに、その後の単行本で“後付け”のように描かれたイラストによって補足が試みられたものの、読者の不信感を払拭するどころか、「言い訳にしか見えない」と批判される事態に。
また、読者が感情的に距離を置き始めたのは、物語の“深刻さ”が増していく中で、希望や救済の描写が極端に少なかったことも大きな要因です。LGBTQ+のキャラクターが苦しむ姿ばかりが強調され、それに対して理解あるマジョリティの存在がほとんど描かれない点にも、「こういう表現ではかえって差別を助長するのでは?」という疑問が投げかけられました。
このように、作品の“テーマ性”が強くなるほどに、読者が求めていたもの――「心が温まる関係性」「料理を通じた穏やかな癒し」とのギャップが拡大。作品の意図は正しくとも、届け方や描写のバランスが崩れたことが、炎上という現象の下地を作ってしまったのです。
3. 28話「山賊事件」が引き金になった理由
3-1. 他人の家で食材を勝手に使う描写がモラル逸脱
『作りたい女と食べたい女』が「炎上」と言われる最大のきっかけとなったのが、第28話で描かれた“山賊エピソード”です。この回では、主人公たちが他人の家に泊まり、そこで相手に許可を取らずに備蓄されていた食材を勝手に使用し朝食を作るというシーンが描かれました。
読者の多くが強い違和感を覚えたのは、この描写があたかも心温まる行動のように美化されていた点です。本来、初めて訪れた他人の家で、無断で冷蔵庫を開けたり、備蓄食材を使ったりすることは、非常識でありモラルの欠如と捉えられても仕方がありません。
SNSではこの行為を「山賊みたい」と揶揄する投稿が広まり、X(旧Twitter)を中心に“山賊回”として炎上。これまで本作を応援してきた読者層からも、「これはさすがに擁護できない」「キャラクターを好意的に描くために現実感を無視している」といった厳しい声が相次ぎました。
本作はもともと、日常の中の些細な幸せや気遣いを丁寧に描いてきた作品だっただけに、この回での“倫理観の崩壊”は物語全体の信頼性を揺るがす大きな問題として受け止められたのです。
3-2. 「やったー朝ごはん!」の描き下ろしは逆効果?
28話での“無断朝ごはん”に対し、後に発売された単行本では補足的な描き下ろしが追加されました。そこでは、食材を使われた側のキャラクターが「やったー朝ごはん作ってもらえた」と喜ぶ様子が描かれており、作品としては「この行為は歓迎されていたのだ」と解釈できるような意図が見られます。
しかし、この描き下ろしが逆効果になってしまったという意見も非常に多く寄せられています。読者の中には、「後出しで正当化されると、かえって誠意が感じられない」「批判に慌てて追加したように見える」といった反応が目立ち、根本的な問題点である“無断であること”は解消されていないという指摘も少なくありません。
さらに、このエピソードのタイミングが悪かったことも炎上を広げた一因です。当時、作品全体がマイノリティ問題など繊細なテーマを扱っていたにもかかわらず、日常のモラルすら軽視する描写が登場したことで、「この作品は本当に現実を丁寧に見ているのか?」という疑念が広がってしまいました。
こうした補足描写による“ごまかし”は、読者との信頼関係をむしろ損ねる結果になってしまったとも言えます。物語の中でキャラクターを守るために現実の常識をねじ曲げてしまうと、読者がついていけなくなるのは当然のことです。
4. 表現のズレと不信感の蓄積
4-1. セクシャリティを「物語の都合」で扱う違和感
本作が扱うテーマのひとつに「同性愛者の生きづらさ」がありますが、この描写の仕方に関しても、多くの読者が違和感を覚えています。特に問題視されているのは、キャラクターのセクシャリティがストーリーの都合で便利に使われているように感じられる点です。
たとえば、新居探しのエピソードでは、主人公たちが同性愛者であることが原因で部屋を借りられないという設定が描かれます。最終的にはLGBTQ+当事者が経営する不動産屋にたどり着くことで解決するのですが、この展開に対して、「現実の問題を過度に悲観的に描きすぎている」との声が多数あがりました。
また、キャラクターが苦しむ姿は多く描かれる一方で、その苦しみからの“解放”や“支援”は具体的に示されないまま進むことが多く、「見ていて辛いばかりで希望がない」「結局、被害者であり続けるしかないという印象を与える」といった意見も見られます。
このように、同性愛者であることがただの“設定”として消費され、現実の複雑さや多様性を描き切れていない点に、当事者や理解のある読者から批判が集まっているのです。物語においてセクシャリティを描くことは重要ですが、それが登場人物の個性や成長ではなく、単なる問題装置として扱われてしまっては、読者の共感も納得も得られません。
4-2. 会食恐怖症や摂食障害の誤認と専門家からの指摘
『作りたい女と食べたい女』は、心理的な困難を抱えるキャラクターを登場させることでリアリティを追求しようとしていますが、その中で描かれた会食恐怖症や摂食障害の描写に対しても、専門家や当事者から厳しい指摘が相次ぎました。
問題となったのは、会食恐怖症を摂食障害と混同して描いている点です。会食恐怖症は「人と一緒に食事をすること」に対する不安障害であり、摂食障害とは異なるメンタルの病です。しかし、作中ではこの2つが曖昧に描かれ、「人と食べられない」→「だから同性愛者であることが関係している」→「そのまま自己肯定感の話へ」と展開していくため、医療的・心理学的な視点から見ると非常に不自然なのです。
読者の中には、実際に会食恐怖症に悩んでいる人も多く、「描かれている解決方法は、むしろ避けてほしいものだった」「“こうすれば治る”という描き方が現実を知らなすぎる」といった声が挙がっています。
また、描写の内容に対する説明やフォローが本編中にはほとんどなく、後になってSNSやコメント欄で“作者の意図”が補足されるような対応も、専門性や信頼性を損なう結果となっています。
繊細な問題を描く際には、フィクションであっても一定の医学的・倫理的リサーチと慎重さが求められます。読者が抱えるリアルな問題を描くなら、なおさら「正しく伝える」姿勢が問われるのです。
5. 絵柄と演出の変化で失われた魅力
5-1. 第5巻以降の絵柄の変化と“作画崩壊”説
『作りたい女と食べたい女』において、読者の間で大きく話題となったのが第5巻以降の絵柄の変化です。特に第44話以降では、キャラクターの表情や体の描き方が明らかに変わり、以前の繊細なタッチから一転して、やや雑に見える描写が増えていきました。
もともとこの作品は、心情表現の細やかさや料理シーンの丁寧な描き込みが評価されていました。初期は、キャラクターのちょっとした戸惑いや嬉しさが、まぶたの揺れや口元の柔らかさで表現されており、それが共感を呼ぶ要素にもなっていたのです。しかし第5巻以降は、その描き方に乱れが生じ、「作画崩壊ではないか?」と一部で囁かれるようになりました。
一時期には、作者の体調不良が原因ではないかとする声もSNS上で見られましたが、後にSNSでの発信内容や活動量から作者の体調不良説は否定的に見られるようになります。むしろ「作品に対する集中力や情熱が低下しているのではないか」というクリエイティブ面での懸念が強まることに。
読者からは、「表情のパターンが限られてきて、どのシーンも同じように見える」「感情の起伏が伝わってこない」といった声が多く寄せられており、ストーリーへの没入感を損なっている原因のひとつとされています。
5-2. グルメ漫画として致命的な料理描写の劣化
この作品の魅力は、料理を通じて女性同士の交流や心の通い合いを描くところにありました。特に初期のエピソードでは、手作りの料理が感情の橋渡しとして丁寧に描かれていたため、「グルメ漫画」としての側面も高く評価されていたのです。
しかし、第5巻を境にその料理描写にも変化が現れ始めます。具体的には、調理中の手元の描写が省略されることが増え、食材の質感や色合いも簡略化されていきました。かつては湯気の立ち上る鍋の中、包丁の入り方、盛り付けの工夫まで細かく表現されていたのが、最近では惣菜を買ってきたような既製品のシーンが増加しています。
とくに読者の批判が強かったのは、「料理が物語の中心にあるはずなのに、肝心の料理が出てこない」エピソードが増えている点です。これはタイトルに「作りたい女」とあるにも関わらず、「作ってないじゃん」という本質的な矛盾を感じさせてしまう要因でもあります。
また、惣菜の描写が増えたことで、キャラクターの気持ちや手間が伝わってこず、「雑に見える」「味気ない」と感じる読者も増加しています。食を通して人と人との距離が縮まる感動的な流れが、描写の希薄さによって台無しになってしまっている印象は否めません。
5-3. 擬音・効果音でのごまかしが読者に与える印象
絵柄や料理描写の簡略化と並行して、目立つようになったのが擬音や効果音の多用です。たとえば、以前は“じゅうっ”という音とともに炒められる具材が細かく描かれていたのに対し、最近では**「ジュッ!」という大きな文字だけが画面に浮かび、調理シーンはほとんど描かれない**というケースが増えています。
このような演出は、リズムを演出するテクニックとして効果的に使われることもありますが、本作の場合は**「描き込み不足を音でごまかしているのでは?」という疑念を持たれてしまいました。読者からは、「料理をしている感が伝わってこない」「手抜きに見える」との意見も多く、擬音や効果音が本来の補助ではなく“主役の代替”になってしまっている点**が問題視されています。
特にグルメ漫画においては、調理工程や料理の完成形を通して読者の五感を刺激し、物語の説得力を高めるのが基本です。そこが擬音やエフェクトに頼り切ることで、料理が“記号化”され、作品の根幹にあるリアリティが薄れてしまっているのです。
読者は細かいところまでよく見ているからこそ、「あ、この作品、もう料理を描くのに力を入れていないんだな」と気づいてしまい、作品への信頼感が損なわれる結果につながっています。これは“気持ち悪い”という違和感にも、密接に関わるポイントです。
6. マイノリティ表現における“理想と現実の乖離”
6-1. 「ステレオタイプ」の強調がむしろ偏見を助長?
『作りたい女と食べたい女』では、セクシャルマイノリティを主軸としたストーリーが展開されており、登場人物たちが日常の中で感じる生きづらさや偏見に直面する場面が多く描かれています。ただ、その描き方に対して「一面的すぎる」「ステレオタイプを強化しているだけでは?」という声が一定数存在します。
たとえば、レズビアンの登場人物が住まい探しのエピソードで「LGBTQ当事者が経営している不動産屋じゃないと入居できない」という極端な設定が登場します。このような描写は確かに現実に存在する課題を反映しているものの、それを唯一の解決策として提示してしまうことで、現実よりも悲観的で閉鎖的な印象を与えかねません。読者の中には、「こういう偏見に直面しているからこそ、もっと可能性のある未来を描いてほしかった」と感じる方も多いようです。
また、キャラクターたちが抱える悩みが「セクシャリティに起因する苦しみ」だけに集約されており、彼女たちの個性や日常生活がその文脈の中に押し込められていると感じる読者もいます。結果的に、マイノリティを“問題を抱えた存在”としてしか描けていないのではないかという疑念が浮上しているのです。
このように、登場人物が抱える問題があまりにも類型的に、かつ極端に描かれることで、「理解を深める」どころか、「こんなに大変な人たちなのか」と逆に距離を感じさせてしまう。それが「気持ち悪い」という検索キーワードの背景にある“読者の違和感”の一因になっていると考えられます。
6-2. “マジョリティ悪者論”への反発と疲弊
本作には、異性愛者や社会的に多数派とされる立場の人たち、いわゆる“マジョリティ”がほとんど登場せず、登場しても冷淡で無理解、時に差別的な存在として描かれる傾向があります。たとえば職場の同僚や不動産屋の対応など、登場するマジョリティの多くが主人公たちに対して無神経で、無理解で、時には攻撃的にさえ描かれています。
もちろん、現実にもそうした差別や偏見は存在しますし、それを作品として描くこと自体に問題があるとは言いません。ただし、その“悪役”の立ち位置を担う人物たちがあまりにも画一的で、理解のあるマジョリティが一人も描かれないという構図は、やはり不自然さを伴います。
特に、第28話での「山賊騒動」以降、読者の目線はより厳しくなっており、「結局この作品はマジョリティを敵として描いて、それを“正義”としてしまっていないか?」という批判も強まりました。こうした構成に対して「読んでいて疲れる」「こっちまで責められている気分になる」という読者の声もSNS上で見られます。
多様性をテーマにした作品において、敵を一方向に決めつけてしまうのは、むしろ多様性の否定に繋がりかねません。マジョリティにも“理解しようとする余地”を描かないまま物語が進んでいくことで、読者の共感や感情移入が難しくなってしまう。これが、作品の「説教臭さ」や「気持ち悪さ」につながっているのではないでしょうか。
6-3. 理解されるための物語が読者を突き放した理由
『作りたい女と食べたい女』は、元々「料理を通じて関係を深める」という穏やかなテーマからスタートしました。そのため、読者の多くは「おいしいごはん」と「静かな百合」が織りなす温かな物語を期待して読み進めていたのです。しかし、物語が進むにつれて、テーマは「セクシャリティの悩み」「社会的偏見」「差別と戦う日常」へとシフトし、読者が想定していたトーンと大きな乖離が生まれました。
もちろん、作品が社会問題を扱うのは意義のあることですし、それによって読者に新たな視点を提供することもできます。ただし、その描き方が一方的であったり、リアリティに欠けたりする場合、読者はかえって「わかってもらいたいという気持ちが重すぎる」と感じてしまいます。
また、作中では、差別や偏見のエピソードが連続的に展開されますが、それに対してポジティブな突破口や希望の描写が乏しく、暗く重たい空気が続く印象を与えます。結果として、「理解されたい」という強いメッセージが読者へのプレッシャーになってしまい、「読むのがしんどい」「押しつけられているように感じる」という反応につながっているのです。
さらに、作者のSNS上での言動や、作中に登場する「批判者に似たキャラ」が登場する展開も、読者を戸惑わせました。作品内での批判への応戦や、メタ的なやりとりが読者との“対話”ではなく“反論”になってしまったことで、物語が本来持っていた「共感性」を大きく損ねてしまったのです。
結果的に、「わかってほしい」という本来の意図が、「わからない人は敵」というメッセージにすり替わって伝わってしまった。この齟齬が、作品に対して“気持ち悪い”と感じさせる決定打になってしまったのではないでしょうか。
7. 作者のSNS対応と“作品内応戦”が燃料に
7-1. 実在批判者のモチーフ疑惑が招いた混乱
『作りたい女と食べたい女』を巡る炎上の中で、特に物議を醸したのが「作品内に登場するSNSアカウントが、実在する批判者をモデルにしているのではないか」という疑惑です。2024年6月に公開されたエピソードでは、主人公たちに対してネガティブな意見を投稿するアカウントが登場し、その言動やプロフィールの特徴が、実際に作品を批判していたユーザーに酷似しているとSNS上で指摘されました。
この疑惑が大きな話題になった背景には、それまで作者がSNS上で行ってきた一連の発言も関係しています。作品への批判が盛んになっていた時期、作者はX(旧Twitter)上でいくつかの投稿に“いいね”を押す形で応答したり、明確に言及せずとも批判的な論調に反応していた形跡がありました。そのため読者の間では、「これはあの人のことでは?」「作者が私怨を作品に持ち込んでいるのでは?」という疑念が強まりました。
創作の中で現実世界の要素を取り入れること自体は珍しいことではありませんが、あからさまに“批判者をモデルにした”と思われる描写が登場すると、受け取る側の印象は一変します。特に、『つくたべ』のように社会的テーマを扱い、マイノリティへの配慮を掲げてきた作品において、そのような描写があると「結局、作品内での攻撃を正当化しているのでは?」という批判が噴出するのも無理はないでしょう。
この一件によって、読者の間では「この作品、ちょっと怖い…」「意見を言ったら報復されるかも」という空気が生まれ、それまで応援していた層までもが距離を置き始める事態となりました。作品の内容よりも、作者のスタンスが注目されてしまう構図が生まれてしまったのです。
7-2. 「正しさ」を描く作者がSNSで見せた“矛盾”
『作りたい女と食べたい女』は、当初から「多様性の尊重」や「理解し合うことの大切さ」といった“正しさ”を中心に据えた作品として知られてきました。登場人物たちが、自身のセクシャリティや生きづらさに向き合いながら、食や日常を通じて他者と関係を築いていく姿に、多くの読者が共感してきたのは事実です。
しかし、作品が批判を受け始めた後、作者自身のSNSでのふるまいが問題視され始めました。具体的には、批判的な意見に対して、名指しはしないものの敵意を感じさせる反応や“皮肉”を含んだ発信が見られるようになり、それが「正しさを説く作家としてどうなのか?」という疑問を呼ぶことになったのです。
たとえば、医学的な描写の誤り(会食恐怖症と摂食障害の混同)について、専門家や当事者から指摘が寄せられたにも関わらず、物語の中では修正が行われず、後付けのコラムで説明するにとどまりました。この対応は、誤解や偏見を助長するリスクを放置していると受け止められ、一部の読者にとっては非常に不誠実に映りました。
また、SNS上では「作品に対しての“誤った”批判には毅然と対応する」といった趣旨の姿勢が垣間見えたこともあり、作者と読者の間に見えない壁ができてしまった感があります。特に、応援していた読者ほど「この作品には信頼してついてきたのに…」という失望が大きく、炎上を一層複雑にしています。
本来、“正しさ”を描く作品であればこそ、制作者側にも一貫した態度と誠意ある対応が求められます。しかし、SNSというパーソナルな場での発信によって、作品の信頼性までもが損なわれてしまった点は、非常に残念と言わざるを得ません。
7-3. 批判者を物語に登場させたことで崩れた信頼感
『作りたい女と食べたい女』では、前述のようにSNS上での批判者を想起させるキャラクターが作中に登場しました。これは2024年6月に掲載された話で、登場人物たちに対して一方的な批判を展開するSNSアカウントが描かれ、あたかも“ネットリンチ”を象徴するような存在として扱われていました。
問題となったのは、ただ単に「ネット上の誹謗中傷」や「無責任な意見」に警鐘を鳴らすのではなく、そのアカウントがあまりにも具体的に“誰か”を想像させるような描写だった点です。プロフィールの文言や投稿内容、使われる言葉のクセなどが、実際に作品を批判していた人物の特徴と重なっており、「これは私のことでは?」と感じた人が続出しました。
このような描写が行われると、作品と現実の境界線が曖昧になり、「作者は個人批判を創作に持ち込んだのか?」という疑念を呼びます。加えて、作中でその批判者が一方的に否定され、しかも物語の中では救済や対話の余地がまったく与えられなかったことで、「これは創作を使った私刑ではないか?」という厳しい声も上がりました。
この出来事が象徴しているのは、作者と読者との“信頼の崩壊”です。フィクションの力を使って、現実の批判者を否定するような展開は、多くの読者にとって「自分も批判したらこう描かれるかもしれない」という不安や恐怖を与え、自由に作品について語れなくなる空気を生み出してしまいます。
本来、創作は自由であるべきですが、その自由を盾に「読者との信頼」を犠牲にすることは、本末転倒です。読者に支持され、共感されてきた作品だからこそ、このような対応はなおさら痛手となり、結果として、作品そのものへの関心や信頼が薄れていく原因にもなっています。
8. 炎上の影響が作品外にも波及──ドラマ版の失策
8-1. ローストビーフ事件と食品安全委員会の指摘
2024年にNHKで放送された実写ドラマ『作りたい女と食べたい女』シーズン1第9話で取り上げられた「ローストビーフの調理シーン」が、予想外の波紋を広げました。このエピソードでは、家庭で簡単にできるローストビーフのレシピが紹介されましたが、調理法の中で肉の加熱温度が不十分であると、内閣府食品安全委員会から公式に指摘される事態となったのです。
具体的には、肉の内部温度が食中毒の原因菌(とくにO-157など)を十分に死滅させるほど上昇していないことが問題視され、「生食用として適切ではない調理法が公共放送で紹介されている」として視聴者や専門家から多くの苦情が寄せられました。NHK側は後日、番組公式サイトで謝罪コメントを掲載しましたが、問題の映像は編集されずそのまま再放送されたことから、さらに大きな疑問や批判を招く結果に。
この一件は、「グルメと食文化を主軸に据えた作品」でありながら、「基本的な食品衛生への配慮すら欠けているのではないか?」という信頼の揺らぎに直結しました。視聴者からは、「食の安全に対する責任感が希薄」「視聴者の家庭に悪影響を与える可能性がある」といった声が多く上がり、作品への不信感を強める出来事となりました。
8-2. 食を扱う作品としての“倫理観の欠如”
『作りたい女と食べたい女』は、もともと「料理を通して心を通わせる百合作品」として高い評価を受けていました。だからこそ、作品世界の中で「食」に関する描写や倫理観が欠けていると感じさせる展開が出てくると、その落差に強い違和感を覚える人が少なくありません。
代表的なケースが、漫画第28話で描かれた“山賊事件”です。このエピソードでは、主人公の一人が他人の家で無断で食材を使って朝食を作るという行動が描かれ、それを肯定的に演出してしまったことが、読者の間で「マナー違反を肯定している」「モラルが崩壊している」と強く批判されました。後に単行本化の際に補足的な描写が追加されたものの、初出時に問題意識がなかった点に、作者や編集部の価値観が問われました。
加えて、ドラマ化された際のローストビーフ事件に見られるように、食の安全性への意識が希薄なまま料理を描いている印象も否めません。作品の本質が「手作りの料理を通して関係を育むこと」だとすれば、衛生管理や食材への配慮など、料理を扱ううえでの基本的な“倫理”がなおざりにされているのは大きな矛盾です。
「ただの創作だから」と軽く見ることもできますが、読者や視聴者は作品内の料理を日常生活に取り入れることもあるため、こうした“描き方のズレ”は大きな不信感につながります。特に“心温まる”が売りの作品であればあるほど、倫理面の欠如は致命的に映ってしまうのです。
8-3. シーズン2で強まる恋愛要素への違和感
NHKで放送されたドラマ版『作りたい女と食べたい女』シーズン2では、当初の魅力であった「料理を通じた関係構築」よりも、「恋愛要素」が物語の中心にシフトしていく様子が見られます。この方向性の変化に対し、視聴者の間では「別作品のようだ」と感じる声が少なくありません。
例えば、シーズン2では親の介護問題や知人の離婚といった重めの社会問題がストーリーの軸として取り上げられ、その中で主人公同士の恋愛がより明確に描かれていきます。もちろん、恋愛を描くこと自体は問題ではありませんが、それがあくまで“料理を媒介とした人間関係”という作品の根幹を圧迫してしまっているように感じられるのです。
さらに、一部視聴者からは「LGBTQ+の問題を強調しすぎていて、テーマが先行しすぎている」「恋愛描写が説明的で、感情移入しにくい」といった指摘も上がっています。当初は、静かな日常の中に“ふと芽生える気持ち”や“自然な距離感”が丁寧に描かれていたからこそ、あからさまな恋愛演出が浮いて見えてしまうのかもしれません。
15分枠という短い放送時間の中で多くの要素を詰め込んだ結果、料理というテーマが薄まり、視聴者が作品に求めていた“癒やし”や“日常のリアル”が消えてしまった──そんな印象を抱く人が増えているのは事実です。恋愛要素の強化が、作品の個性と繊細さを損ねてしまったのではないかという懸念が、ここには色濃く表れています。
9. なぜ「作りたい女」が「惣菜買ってきた女」になったのか
9-1. タイトルと中身の乖離が意味する“迷走”
『作りたい女と食べたい女』というタイトルは、一見して非常にキャッチーで、読者に「料理を介して育まれる関係性」を連想させます。実際、連載初期にはその名にふさわしい内容が多く、主人公たちが手作りの料理を通じて距離を縮めていく様子に、多くの読者が共感や癒やしを感じていたようです。
ところが、物語が進むにつれて、「作る女」と「食べる女」の関係性やその描写が大きく変化していきました。とくに第5巻以降では、手の込んだ料理の描写が減少し、惣菜や既製品を買ってきて簡単に済ませるシーンが目立つようになります。この変化は、読者から「タイトル詐欺では?」という反発を招く一因となりました。
また、「作る」ことに込められたはずの思いや、行為としての意味がどんどん希薄化していく様子も指摘されています。料理が単なる舞台装置になり、キャラクターの心情やストーリー展開に深く結びつかなくなってしまったことで、タイトルと中身の間に明らかな乖離が生じてしまっているのです。
たとえば、第28話で主人公たちが他人の家に泊まり、無断で食材を使って朝食を作るという描写がありました。このシーンは「山賊」と揶揄され、SNS上で大きな批判を呼びました。読者がタイトルに期待したのは、「思いやりのこもった料理を通じた交流」であり、「マナーを逸脱した行動を肯定的に描くこと」ではなかったはずです。こうしたギャップが、「気持ち悪い」という検索ワードにつながっている側面もあるでしょう。
つまり、「作りたい女と食べたい女」というタイトルが掲げる世界観と、作品が実際に描いている内容のズレは、物語全体の“迷走”を象徴しているとも言えるのです。読者が求めているものと、作品が届けようとしているものがすれ違い始めた地点こそが、炎上や批判の温床になっているように見受けられます。
9-2. 繰り返される展開と“ネタ切れ”の兆候
物語の展開が進むにつれ、読者の間では「またこのパターンか…」という声が徐々に増えてきました。具体的には、キャラクター同士のすれ違いや誤解が発生し、それを誰かの一言や料理をきっかけに解決する、という流れが何度も繰り返されており、展開に新鮮味が感じられなくなっているのです。
とくに、第40話以降に顕著だったのが、「同性愛者であることの苦悩」や「理解されないことのつらさ」を軸に据えたストーリー展開が、ほぼ定型化している点です。もちろん、テーマ自体は社会的意義があるもので、真摯に向き合おうとする姿勢は評価されるべきですが、ほぼ毎話そのような構図が続くと、読者は「また同じような話か」と感じてしまいます。
さらに、キャラクターの心理描写もワンパターン化しています。特定のキャラクターが悩みを抱え、それを長々と独白し、最後は他者の受容によってなんとなく収束する…というプロットが何度も登場します。これにより、ストーリーに緊張感や驚きが生まれにくくなり、「読まなくても展開が読める」と感じさせてしまっているのです。
また、料理描写の面でも同様の“繰り返し感”が問題視されています。初期には細かく描かれていた調理工程や食材の描写が、最近では簡略化され、既視感のある献立が続いています。たとえば、炒め物や煮物のような家庭料理が多く登場しますが、それらが物語のテーマと結びついているかというと、必ずしもそうではありません。ただ出てくるだけ、という印象を与えてしまっているのです。
読者の中には、「作者がアイデアに詰まっているのでは?」と懸念する声も出始めています。これは単なる批判ではなく、「好きだったからこそ残念に思う」という声も多く含まれています。
このように、ストーリー、キャラクター、料理、テーマのいずれの面でも“繰り返し”が続いており、結果として「ネタ切れ感」が否応なく漂っているのが現状です。その積み重ねが、じわじわと読者の離脱や否定的な検索キーワードを引き寄せていることは、否定できません。
10. SNS世論と作品の分断:評価と批判の二極化
10-1. 支持者の声に共通する“初期の良さ”
『作りたい女と食べたい女』を今も支持し続ける読者には、ある共通点があります。それは、作品初期に描かれていた“心温まる日常”と“手料理を通じたやり取りの丁寧さ”に強く惹かれているということです。
連載初期の『つくたべ』は、百合要素をベースにしながらも、決してセンセーショナルに偏ることなく、登場人物の内面をじっくりと描いていました。たとえば、ふみちゃんが料理を通して自分を少しずつ表現していく過程や、ゆきちゃんがその手料理に素直に感動する様子は、「言葉にしづらい感情を食卓で交わす」という、非常に静かでリアルな関係性を感じさせました。
また、料理の描写も非常に魅力的でした。1話目で登場した「じゃがいものきんぴら」や、ふみが手間をかけて作った「鮭のホイル焼き」などは、食べるシーンの空気感まで伝わってくるような繊細な絵と表現で、多くの読者に「料理漫画としての期待」を抱かせた要素でもあります。
この“等身大のやさしさ”や“非当事者でも理解できる温かい人間関係”こそが、初期からの支持者にとっての本作の魅力でした。社会問題をテーマにしながらも、説教臭くならずに物語として受け止められた点が、多くの読者の共感を集めた理由なのです。
10-2. 批判者に共通する“現実との乖離”感覚
一方で、本作に対して批判的な意見を持つ読者の多くが口を揃えて指摘しているのが、「現実との乖離」です。この感覚は、主に作品が後半に進むにつれて浮き彫りになった、登場人物の行動や言動の“リアリティのなさ”に起因しています。
たとえば第28話では、ゆきとふみが他人の家で勝手に備蓄食材を使って朝食を作るという展開がありました。このシーンはネット上で「山賊」などと揶揄され、多くの読者がモラル面に強い違和感を覚えました。物語の中では好意的に描かれた行為が、現実では明確なマナー違反であるというギャップが、「気持ち悪い」とまで言われる原因になってしまったのです。
さらに、セクシュアルマイノリティに関する描写についても、現実の当事者から「ステレオタイプすぎる」「現実的でない」といった批判が相次ぎました。特に、同性カップルが新居を探すエピソードでは、理解ある不動産屋に出会うまで全く解決策が見えないという描写に対し、「悲観的すぎる」「救いがなさすぎる」といった声が集まりました。
このように、読者が現実に即して考えた時に、「本当にこうなるか?」「実際の人間関係や生活とかけ離れていないか?」と感じてしまう瞬間が増えたことが、批判の根底にある“違和感”へとつながっているのです。
10-3. 「見たい作品」と「届けたい作品」のズレ
支持と批判がここまで激しく分かれる最大の理由は、読者が「見たいと思っていた作品」と、作者が「届けようとする作品」の間に、大きなズレが生じていることにあるのではないでしょうか。
もともと本作には、「料理を通じたゆるやかな交流」と「自分の居場所を見つけていく女性たちの物語」という期待が寄せられていました。ところが物語が進むにつれ、マイノリティの社会的な困難、トラウマ、恋愛における同意、そして親の介護や職場での差別といった、かなり重たいテーマが中心になっていきます。
もちろん、こうしたテーマを扱うこと自体に問題はありません。しかし、読者が「ほっこりできる百合グルメ漫画」として読み始めたのに、途中から“社会問題を啓発するフィクション”のような方向に舵を切ったことで、多くの読者が「これは自分の読みたかった作品とは違う」と感じるようになってしまったのです。
さらに、物語後半では同じような展開や台詞の繰り返しが見られ、「ネタ切れでは?」という声や、表現の粗さに対する不満も目立ちました。この“作り手の伝えたいこと”が強く前に出すぎる一方で、“読み手が求めていたもの”が置き去りにされている印象が、多くの読者を戸惑わせているのです。
この「ズレ」が是正されないまま続いていることが、炎上や“気持ち悪い”といった厳しい言葉につながっている――そんな構造が今の『つくたべ』には見て取れます。
11. 終章:多様性と配慮の時代に問われる「創作の責任」
11-1. 作品が目指したものと、実際に伝わったこと
『作りたい女と食べたい女』は、もともと「料理」を媒介にして、人と人との距離を縮める物語として始まりました。同性同士の関係性に焦点を当てつつ、レズビアンである主人公たちの心の機微を料理とともに描くことで、多様性や受容というテーマを丁寧に表現しようとしていたのです。特に初期は、「作ってあげたい」「食べてもらいたい」という気持ちを通して、性別や恋愛対象にかかわらず“人の温かさ”が伝わってくる作風が支持されていました。
しかし、作品が進行するにつれて、その方向性には変化が見られます。特に5巻以降は、恋愛やジェンダー、マイノリティの生きづらさといった社会問題の描写が増え、物語のトーンが重くなりました。28話の「山賊」問題、つまり登場人物が他人の家で無断で食材を使ったシーンを皮切りに、モラルや現実感の欠如が目立つようになり、作品に対する読者の受け取り方も大きく変わります。
作品としては「多様性を伝えたい」「マイノリティのリアルを描きたい」といったメッセージを込めていたのかもしれませんが、実際には「同性愛者=苦悩している存在」という一面的な表現にとどまってしまい、リアルな当事者から「悲観的すぎる」といった指摘が相次ぎました。また、会食恐怖症の描写についても、摂食障害と混同したような演出が見られ、専門家からも誤解を招くと批判されています。
つまり、作品が目指したであろう「理解と共感を促す物語」は、実際には「偏見を助長するような描写」や「非現実的な設定」によって伝わりきらなかった側面が大きく、そこに読者とのすれ違いが生じたのです。
11-2. 読者との“対話”を断ったことの代償
読者との信頼関係を維持する上で重要なのは、作品内外での「対話的な姿勢」です。しかし、この作品においては、その“対話”がいくつかの局面で断たれてしまった印象があります。特に目立ったのは、SNSでの作者の対応です。
2024年6月に公開された回では、SNS上で批判的な投稿をするキャラクターが登場し、実在の批判者をモデルにしているのではないかという疑惑が広まりました。このような表現は、「批判する読者=悪者」という構図を匂わせており、商業作品としての中立性や品格を損なう結果となりました。
また、医学的な誤りに対しても、作中での修正ではなく、後付けのコラムで釈明する形が取られました。これは「作中の描写はそのままに、読者の理解だけを修正する」という形式であり、真摯に批判と向き合ったとは言い難いものです。
こうした姿勢は、「読者の声に耳を傾ける気がない」「都合の悪いことはスルーする」という印象を与えてしまい、炎上を鎮めるどころか、さらなる火種となりました。作品に対する不信感は、物語の中身以上に、作者の振る舞いや反応によって深まっていったのです。
11-3. 今後、再評価されるには何が必要か
これまでの騒動や批判を乗り越えて、『作りたい女と食べたい女』が再び評価されるためには、いくつかのポイントが必要になります。まず一つは、物語の“芯”を見直すことです。初期に評価されていたのは、「料理を通して人とつながる」温かさでした。その魅力が再び前面に出てくることで、作品の本来の良さが復活する可能性があります。
次に、批判されてきたテーマ――セクシャリティ、精神疾患、マイノリティ――の描写について、より現実に即した慎重な表現が求められます。専門家の監修を入れる、当事者の声を反映するなど、信頼を取り戻すための努力が必要です。「正しさを主張する物語」ではなく、「一緒に考える物語」として再構築することが、再評価への第一歩となるでしょう。
そして何より、読者との信頼関係を再び築くためには、SNSでの姿勢も含めた“開かれた態度”が求められます。炎上を恐れて逃げるのではなく、真摯に意見を受け止める姿勢が見えれば、読者もまた作品に向き合い直すきっかけを得るはずです。
つまり、再評価されるには「原点回帰」と「対話の再構築」が不可欠です。ただ物語を描くだけではなく、その背景にある誠実な姿勢があってこそ、作品は再び多くの読者の心をつかむことができるのだと思います。
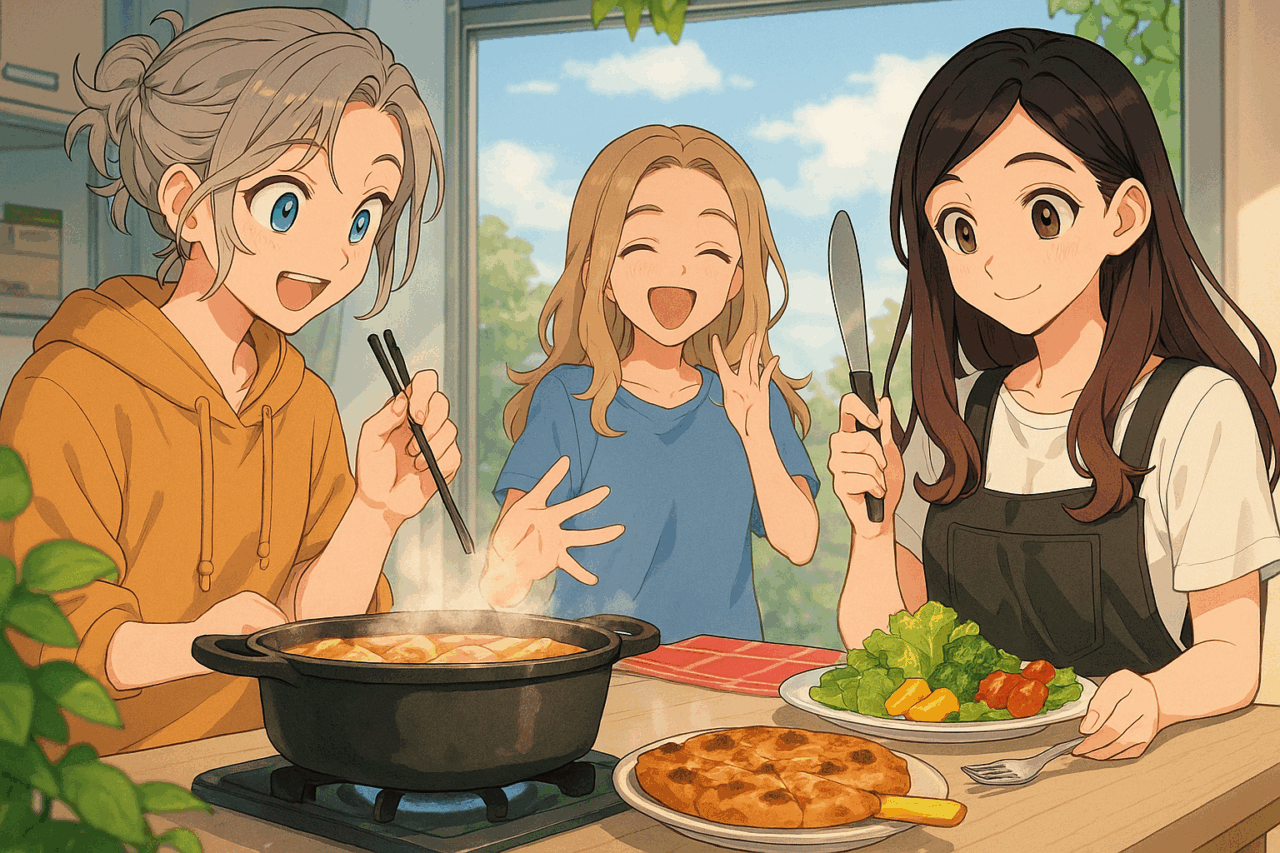


コメント